講師 山名尚志
(株式会社文化科学研究所代表)
日本における「寄付金」社会の動向
個人や企業の善意に基づいた寄付による非営利の自由な活動が活性化することで、社会はより多元的で寛容なものになるのではないか。1980年代後半、米国の寄付社会をモデルにこうした考えが日本社会でも広まり、1990年には経団連の「1%(ワンパーセント)クラブ」が設立された。ちなみに、同年には芸術文化を支援する企業メセナ協議会も設立されている。
当時、課題となっていたのが、こうした寄付を受け入れ、社会貢献活動を行う受け皿の法的整備だ。米国では、税制優遇を受けられる非営利法人が、内国歳入庁(IRS)に届け出るだけで簡単に設立できた。しかし、日本では、1896(明治29)年の民法制定以来続いてきた、旧態依然の財団と社団しかなく、その設立や活動の自由は極めて制限されていた。
この状況に風穴を開けたのが、阪神・淡路大震災のボランティア活動を契機に、1998年に民法34条の特別法として成立した「特定非営利活動促進法(NPO法)」だ。2006年には公益法人制度を抜本的に見直す民法34条に代わる関連3法が成立。自由で多様な非営利活動を拡大していく法的な基盤が整備された。
一方、寄付者の動向はどう変わったのか。2009年には関係者が発起人となってNPO法人日本ファンドレイジング協会が設立され、現在、「2020年、善意の資金10兆円」を掲げて推進活動を展開している。同協会が発行している「寄付白書」によると、2014年の日本の個人会費・寄付金総額は、1兆538億円。米国の寄付金総額が2015年で3,732.5億ドル(1ドル114円で42兆4,479億円)(*1)であるのと比較すると、GDP規模(2015年で米国は日本の4.4倍)の差を踏まえても、いかにも少ない。こうした中で新たに注目されているのが、自らの遺産を法定相続人にそのまま相続させるのではなく、「遺言書」により残したいところに残すという「遺贈」だ。
日本財団 遺贈寄付サポートセンターの立ち上げ
その遺贈により社会貢献活動を活性化しようと、日本財団が2016年4月1日に開設したのが、「日本財団遺贈寄付サポートセンター」(以下、サポートセンター)である。日本財団は、「よりよい社会のために、新しい仕組みを生み出し、変化を引き起こす、そのアイデアと実践=ソーシャル・イノベーション」を掲げ、「みんながみんなを支える社会」の実現を目指し、さまざまな支援プロジェクトを展開してきた。特に東日本大震災以降、いち早く目標額300億円の「震災復興支援特別基金」を立ち上げ、文化芸術ジャンルでは事業指定寄付により「地域伝統芸能復興基金」を設置し、流出した民俗芸能の道具・衣裳などの支援を行うなど、寄付による社会貢献活動を牽引してきた。
今回のサポートセンター設立のきっかけにも東日本大震災が関わっている。日本財団では、2005年から遺贈寄付を受け入れ、年間100件程度の問い合わせがあったが、震災を境に相談が急増。また、2011年に匿名の女性から1億5,000万円の遺贈(*2)の申し入れもあり、専門家チームによる相談窓口の必要性を痛感。一方、日本ファンドレイジング協会、あしなが育英会、日本盲導犬協会や専門家等と「遺贈寄付推進会議」(*3)でも研究を重ね、日本財団としてサポートセンターを設立した。
2016年3月には、日本財団として全国40歳以上の男女にインターネットによる「遺贈に関する意識調査」(有効回答2,521)を実施。その結果、4.6%が「遺贈したい」と回答し、「興味関心がある」を含めると30.9%に遺贈の意向があることが明らかとなった。また、遺贈目的としては、「貧困家庭の子どもの教育支援」(39.4%)、「難病で苦しむ子どもと家族の支援」(37.8%)、「災害時の緊急支援や復興支援」(30.4%)が多く、「地域再生や地方創生に関わる活動」(11.2%)や「学術、文化、芸術またはスポーツの振興を図る活動」(10.6%)にも1割程度が関心を寄せていた。一方、「遺贈」に不可欠な「遺言書」については、58.0%が準備は必要だと思うとしながら、全体の3.2%しか準備をしていないことも明らかになった。
また、終活に関して「家族や友人とは話しにくい」と回答する人が30.3%と高く、「無料で相談できる場所があれば相談してみたい」(23.7%)、「気軽に相談できる場所や人があれば相談してみたい」(22.3%)、「無料でいろいろな相談にのってほしい」(18.4%)など、家族や友人以外での相談を求める回答が多くあった。
こうしたアンケート結果を踏まえて立ち上げたのが、電話やインターネットにより気軽に「無料相談」をできるサポートセンターだ。また、遺言の普及を目指して、1月5日を「遺言の日」に制定するなど、キャンペーン活動をスタートした。
サポートセンターの活動
サポートセンターは、現在のところ7名の電話相談員、税理士や弁護士などの専門家でチームを構成し、運営されている(必要に応じて外部専門家と連携)。日本財団への遺贈では、「貧困家庭の子どもの教育支援」「難病で苦しむ子どもと家族の支援」「災害時の緊急支援」「開発途上国の医療・教育支援」「開発途上国の障がい者支援」のほか、冠基金(*4)の設立など遺贈先・終活などにまつわるさまざまな相談に応じている。サポートセンター開設に伴い、4月1日に新聞全面広告で周知したところ、大きな反響があり、2017年1月10日現在の問い合わせ数は、電話で420件強、ウェブで80件強の計514件だった。
昨年9月までの問い合わせ(計480件)の相談内訳は、「遺贈・寄付」(162件)、「相続全般」(72件)、「遺言書」(71件)、「不動産の処分・売却など」(49件)、「家族や親族との関係性」(46件)となっており、遺贈先の相談よりも終活そのものについての相談が多数を占めた。遺贈の性格上、問い合わせがすぐに寄付に繋がるわけではない。さまざまな相談を経て、遺言書を作成し、相談者が逝去されてから初めて遺贈が具体化する。今後について、サポートセンターの高木萌子さんは、「相談者との信頼関係を構築し、遺贈先の社会貢献活動の現場を視察していただくなどの理解を深めながら、無料相談から遺贈への流れを強化していきたい。また、遺贈者のための会員組織など、新たな仕組みも考えていければ」と話す。
法定相続人がおらず、国庫に回収される遺産は年間300億円にも上る。今後の高齢者の増大などを踏まえると、遺贈可能な遺産の規模はさらに大きくなる。このお金を、本人の確かな遺志に基づき、資金を必要としている社会貢献活動とうまくマッチングできれば、もうひとつの新たな社会システムになるに違いない。
図1 個人寄付総額・会計総額・寄付者率の推移
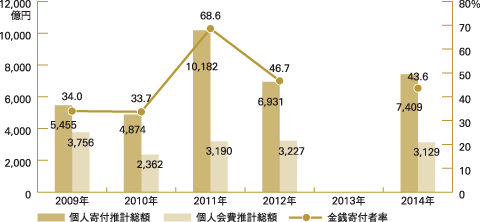
注:2013年は調査なし。2011年は震災関係の寄付(5,000億円)を含み、金銭寄付者率も震災関係以外の寄付者率(29.4%)を含む。
出典:日本ファンドレイジング協会『寄付白書2015』
図2 どのような目的・使途に対して遺贈をしたいか(複数回答)
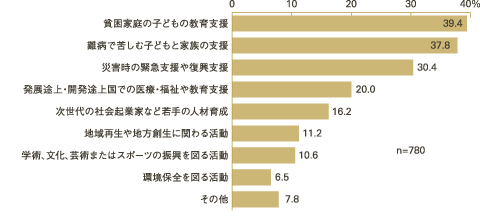
出典:日本財団「遺贈に関する意識調査」(2016年)
図3 どのような団体に遺贈したいと思うか(複数回答)
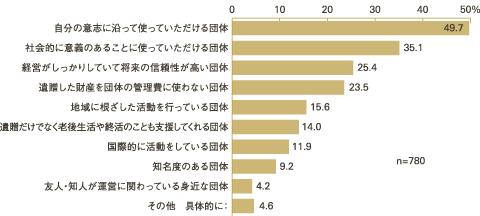
出典:日本財団「遺贈に関する意識調査」(2016年)
●日本財団 遺贈寄付サポートセンター
https://izo-kifu.jp/
●自筆遺言書作成キット
上記サイトから無料申し込みが可能。
https://izo-kifu.jp/present
*1 「Giving USA 2016」より。
*2 匿名女性の遺贈は、ミャンマーのヤンゴン市内の知的障害者向け施設建設費に充てられ、知的障害者および指導者のトレーニング事業が行われている。
*3 「遺贈寄付推進会議」は、その後、全国レガシーギフト推進検討委員会を経て、2016年11月に遺贈寄付の相談・紹介・受入れの全国的なプラットフォームである「全国レガシーギフト協会」に改組。
https://peraichi.com/landing_pages/view/legacygiftassociation
*4 寄付者の名前等を自由に名称を決められる基金。使途は、寄付者が希望した分野の社会貢献活動に使用する。原則100万円以上の寄付で設置。
