講師 片山正夫
(セゾン文化財団 常務理事)
今年の12月から、いよいよ新しい公益法人制度が施行される。すでに2006年、関連する3つの法案(*1)が成立、公布され、その後いくつかの政令や省令が発表された。今回の改正は、1896(明治29)年の民法制定以来続いてきた我が国の公益法人制度を抜本的に見直すものであり、文化・芸術の振興に関わる活動にも大きな影響をもたらすものと考えられる。そこで本稿では、制度改正の背景や狙い、その意義を踏まえつつ、この改革によって具体的に何が変わるのか、文化・芸術振興の現場で何を考えておく必要があるかについて、2回に分けて検討していきたい。
●今なぜ改革なのか
今回の改革の最大の目的は、「民間の担う公共」を我が国の社会に根づかせていくことだ。その背景には、社会のさまざまな問題に政府が対応しきれなくなってきたことがある。経済成長の鈍化や少子高齢化により、政府に財政的余裕がなくなりつつある上、問題そのものが多様化してきており、政府の一律・公平なやり方だけではもはや十分な効果が期待できないのだ。思えばこのことを端的に示したのが阪神・淡路大震災であった。当時の民間ボランティア団体による迅速で柔軟な救援活動は、逆に「政府の限界」を私たちに強く認識させる契機となった。
しかしながら我が国では、これまで公益的活動は基本的に政府の役割とされてきた。そのため民間が民間の発意で公益法人(*2)を設立するのにも、政府の「許可」が必要であった。行政において「許可」とは禁止行為の解除を意味する。つまり民間人による公益活動は明治以来、原則として“禁止”だったのであり、何を許し何を許さないか(あるいは何が公益であるか)は役所が決めてきたのだ。もともとの思想がこのようなものだから、法人設立のハードルは高く、かつその基準自体も曖昧だ。また設立された後も「主務官庁(*3)」が法人の活動を、箸の上げ下ろしに至るまで“指導”することになる。これでは本来自由であるべき民間の公益活動を阻害してしまうことになりかねない。そこで、公益性について明確なルールを定め、各法人の内部統治を強化することで、官による過剰なコントロールを止めてしまおうというのが今回の改革なのである。
●改革のアウトライン
さて制度改革の骨子は次のとおりである。
①準則主義(*4)(登記)により設立できる一般的な法人制度を創設する(一般社団法人と一般財団法人の2類型がある)。
②民間有識者から成る委員会(公益認定等委員会)が上記法人の公益性を判断し、公益認定を受けた法人は公益社団法人、公益財団法人となる(以下、新公益法人と呼ぶ)。
なお今回改革の対象となったのは、現在の公益法人と中間法人(*5)だ。が、これは本来不自然な組み合わせと言うべきだろう。両者は異なった性格をもつ法人だからである。図は法人類型を「公益/非公益(*6)」「営利/非営利(*7)」の別で分類したものだが、これを見ても、今回の改革の対象が、「公益性の有無」というラインを跨いでしまっていることがわかる。そのため①でいう一般法人は、あらゆる目的のものが含まれることになり、法人としての性格はいまひとつ、はっきりしないものとなってしまった。
しかしともあれ、法人設立の段階では、行政による判断はもはや介在しなくなった。設立後においても新公益法人を監督する役割を担うのは公益認定等委員会なので、ここに明治以来続いてきた許可制、主務官庁制は廃止されたことになる。「設立」と「公益性の認定」が、これまでと違って別々に行われるようになったわけだ。
公益性の認定を行う機能が単に行政から第三者機関に移っただけではなく、今まで不透明であったその基準が法律で明文化され、さらにガイドライン等に細かく記述されることになった点も重要だ。何が公益で何が公益でないのかという、ともすれば神学論争に陥りそうな問いに、できる限り客観的に答えようと試みた関係者の努力は評価に値するだろう。
新制度の施行に伴い、現在の公益法人は本年12月をもって、自動的に特例民法法人という特別のステータスをもつことになる。特例民法法人の間は従来どおり主務官庁に監督され、制度的にも今までと何も変わるところはない。これは5年間を限度とする移行のための措置で、この間に公益認定を受け、新公益法人になればよい。もちろん税制等のメリットを望まないのなら、認可を受けて一般法人になる選択肢もある。ただし、何もしないで5年を経過すると強制的に法人は解散となるので、計画的な準備が必要だ。
●税制による支援
以上が新しい法制度のあらましであるが、これが改革の骨格であるとするなら、血肉となるのは税制だ。そのなかで、特に今回の目玉といえるのが寄付税制の改正である。
これまでの我が国の寄付税制は「寄付をさせないための税制」であったともいわれる。個人にしろ、企業にしろ、寄付した額を自分の所得から控除できるとなれば、では寄付をしてみようかという気になるものだ。ところがこれまでわが国では、そこに寄付をした際に所得控除を受けられる法人の数が極めて限定的であった。今の公益法人がその資格を得るには特定公益増進法人になる必要があるが、その門は非常に狭く、しかも資格取得の条件も不透明だ。現在この資格を付与されている公益法人は900程度しかない。これはNPO法人においても同様で、特定公益増進法人に相当する認定NPOの資格をもつのは、3万3000近くに増えたNPO法人のうちわずか60程度である。
今回の改正により、公益認定を受けた新公益法人はすべて特定公益増進法人となる。新公益法人に寄付された財産は、個人の場合、所得の40%まで控除可能だ。企業からの場合は、一般寄付枠が2倍になるだけでなく、その枠自体も拡大された。
このほか地方税(個人住民税)においても、寄付金控除の対象となる寄付金の範囲が広がる。所得税の適用対象の中から、これを地方自治体が条例で定めることができるのである。これまで地方税は寄付金控除となる対象法人はほとんどなく、適用下限額も10万円と高額(今回5000円になった)だっただけに、こちらも大きな変化といえる。我が国も今回の改正で、ようやく寄付文化醸成に向けての条件が整備されてきたと言えそうだ。
このほか法人自身に課せられる税についても、いくつかの大きな改正があった。そのなかで特に注目されるのが、法人税の課税範囲だ。税法で定められた収益事業にだけ課税される点は変わらないが、これまではこれに該当すると、たとえ公益目的事業でも課税対象であった。例えば演劇公演は「興行業」に該当するから課税される。しかし新制度では、公益目的事業として認定された事業であれば、仮に税法上の収益事業(*8)であっても課税されることはなくなった。当然と言えば当然のことだが、ここが是正された意味は大きい。
●強化される内部統治(ガバナンス)
先にふれたように、今回の改革の趣旨は官によるコントロールをなくしていく点にあるが、それに代わって重要になるのが各法人の内部統治(ガバナンス)だ。これまで公益法人の内部統治はと言うと、お世辞にもきちんと機能していたとは言い難かった。財団法人を例に取ると、理事(会)・評議員(会)・監事は、一応必ず設けることになっており(とはいえ法律で義務付けられているのは理事だけだが)、各々の役割も寄附行為上規定されてはいるものの、現実には名誉職的なものであったり、就任の際の説明が不十分であったりして、責任分担は曖昧であった。
今回の改革の源流は実は行政改革にあり、不祥事の目立つ官製天下り法人をどうするのかという点に問題意識が置かれていたのだが、そこでも一部の執行者の暴走を許すガバナンスの甘さがつとに指摘されてきたところでもあった。
新制度では評議員会が法人の最上位にいて重要事項を決定し(*9)、業務執行においては理事(会)がすべての責任を負うという形となった。理事の任命・解任権は評議員会がもつので、今までのように理事が評議員を選ぶということは許されない。理事・評議員が任務を怠り損害を生じた際の賠償責任も法律に明記され、会議への代理出席や委任状での出席も認められなくなる。これまでのやり方に慣れた法人の役職員には、かなりの“意識改革”が求められることになるだろう。
主な法人の状況と今回の改革の対象
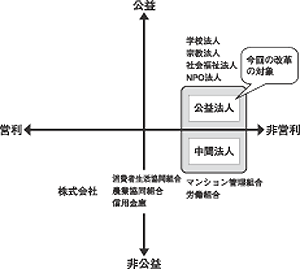
*1 「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」「公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律」に整備法を加えた三法。
*2 現在(改正前)の公益法人は民法34条以下に規定されており、人の集合体である社団法人と、財産の集合体である財団法人がある。総数は約2万5千。なお特別法で設立される学校法人や社会福祉法人なども税制上は「公益法人等」である。
*3 その法人が目的とする公益事業を所管する官庁。中央官庁である場合と都道府県である場合がある。
*4 株式会社のように、定められた要件を満たせば必ず設立が可能ということ。
*5 同窓会のように、営利を目的とせず、メンバーの利益を追求する法人。
*6 不特定多数の利益(公益)をめざすものか、そうでないかの区分。
*7 利益や剰余金を関係者に分配する(営利)か、しないかの区分。
*8 33(改正後は34)の業種が列挙されている。収益を目的として行っているかどうかとは関係なく、外形的に判断される。
*9 社団法人の場合はこれまでどおり社員総会がその機能を担う。
●行政改革推進事務局ホームページ
「公益法人等改革について」
http://www.gyoukaku.go.jp/about/koueki.html
●財団法人公益法人協会
http://www.kohokyo.or.jp/
